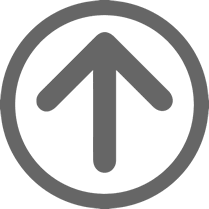(執筆日:2008年07月31日)
昼休みが半分ほど過ぎた頃、津王が勝手に、僕の目の前にある席の椅子を拝借した。満面の笑顔でノートを差し出してくる。
「ありがと。助かった」
「どういたしまして」
黙々と一人で弁当を食べていた僕は、手短な返事だけをして素っ気なくノートを受け取る。
そんな僕を、津王がジロジロと不躾に眺めてきた。
「なに?」
軽く苛立った声で僕は問いかける。
すると津王は、まっすぐな視線で、まっすぐに質問してきた。
「なんで多嶋はいつも一人でいるの?」
こんな質問は珍しくない。小さい頃からよくあった。
だから僕はいつもこう返事をする。
「一人が好きだから」
「なんで?」
間髪入れずに次の質問。
僕は少し困惑した。
「なんでって、理由なんてないよ」
「一人でいたらつまんないじゃん。俺、多嶋の笑った顔、見たことないよ」
「べつに笑いたくないし」
「なんで? 笑うと楽しいよ」
だから嫌なんだ。
だから苦手なんだ。
そうだ。思い出した。ずっと前もそうだった。
幼稚園の頃。
だから僕は腹が立って、意地悪して、こいつを泣かせたんだ。
友達ごっこをやりたがるこいつにムカついて。
「いいから、僕のことはほっといてもらえないかな」
冷静な声で、冷たく突き放すように、津王に向かって言葉を放った。
津王から笑顔が消え、まるで傷つけられたみたいな顔を一瞬だけ見せて、戸惑った声を出した。
「あ、ごめん。迷惑だった?」
「迷惑だよ。人それぞれなんだから」
「ホント、ごめんね? あと、ノートありがと。ホントに助かった」
僕を怒らせたと思ったのか、焦った素振りで席を立ち、そそくさと去って行く。
少し意気消沈しているような背中を眺め、僕はそっと息をついた。
きっともう、これで二度と近づいて来ないだろう。
友達ごっこなんてやりたくない。
もうすぐ死ぬ奴となんて。