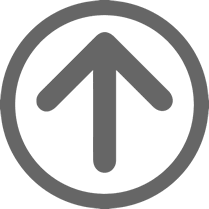(執筆日:1998年04月28日)
弥帋の声に誘導されながら、高嶺は意識の奥へ奥へと沈んでいった。
表層意識の壁を越え、潜在意識の横たわる場所へと移動していく。
やったことはないが、瞑想とはこんな感じだろうかと思った。
弥帋の声は耳に心地よかった。不思議なことに安らかな気持ちになれる。
夢の中を漂うように、高嶺は意識の奥底を歩いてみた。実際に足で歩いたわけではなかったが、その表現がいちばん似つかわしかった。
この状態に入る前、そして入った今でも、体内の魏魔が嫌がっているのがわかる。
意識の底は混沌としている。はっきりした形は判断できなかったが、雑多にいろいろな物が浮いている。
そこに、ずっと目をそむけてきたものがあった。
「……」
高嶺は目をそらす。見たくなかった。
家族との確執。
高嶺の家族は、両親と姉と高嶺で構成されている。
高嶺が幼い頃には祖父と祖母も一緒に暮らしていたが、小学校に入ったばかりの頃に祖母が老衰で命を落とした。それにつられるようにして、祖父も逝った。
高嶺の父親は仕事人間で、ある有名な商社に勤めている。高校も大学もランクの高いところを出ていた。優秀で、出世街道を走っている。
家庭のことはすべて妻に任せ、子供たちとはロクに会話もしない毎日が続いていた。
口を開く時には成績のことばかりで、一緒に遊んでもらった記憶はない。
母親の方は子供の教育に熱心で、父親のようなエリートに育てあげるのを使命としているかのように、子供たちを塾三昧の生活へと陥れていた。
姉弟はどちらも頭の出来がよく、外見の方も申し分ない。
ところが少しでも成績が落ちれば、両親の叱責が待っているので油断はできなかった。
両親からよく褒められる姉と違って、高嶺は小さい頃から両親と気が合わない。子供の気持ちを考慮しないで、親の望みだけを押しつけられるのが高嶺は嫌だった。
姉は「いい子」なのではなく、「いい子」を演じて褒められていた。
それが出来ない高嶺に、よく「バカね」と言う。
「要領よくうまくやればいいのよ。裏で何やったって、どうせあの人たちにはわかんないんだから。あの人たちの大事なのは、成績や評価だけ。あたしたちがどんな性格してて、どんなことが好きかなんて、まったく興味ないのよ」
高嶺はそんな姉のことも好きではない。
塾へ行くフリをして、派手な私服に着替えて、他の仲間とつるんで妙なアルバイトをしているらしい。詳しいことを高嶺は知らなかったが、たまに高価な服やバッグを買ってきて、親に見つからないように隠しているのには気づいている。
だから、
「姉さんの方は先生方の評判もいいし、お母さんの言うこともよく聞いてくれるわ。なのにどうして高嶺は、お母さんのことわかってくれないの?」
何度そう言われただろう。子供のことをわかってないのは、あんたたちの方だろう、と怒鳴りたくなったことは何度でもあった。結局口にしなかったのは、何を言ったとしても、高嶺の言葉を両親に信じさせるのは難しいと感じたからだ。
父親とも話が噛み合わず、たまに喋っても口喧嘩のようになるだけだった。
高校を卒業したら家を出ようと思った。
クラスメートの和端が、大学入ったら独り暮らしをする、と聞いて、行き場のなかった高嶺は即座にふたり暮しを提案した。和端は戸惑うこともなく承諾し、今の生活が始まったのだ。
「血がつながってるんだから、絶対に仲良くなれないなんて、そんなことないと俺は思うよ?」
和端の言葉を思い出し、高嶺は意識の海を泳ぐ。
相入れることのできない家族、というのもあるのだ、と高嶺は常々思っている。
和端の家は暖かくて幸せで、仲がいい。だから和端にはわからないのだ。
意識の奥へと進むにつれて、見たくない感情や気持ちが見えてくる。
嫉妬があった。
高校の頃、和端の家に誘われることが何度かあった。
友人の多い和端は、よく家に友達を呼んでいた。その仲にまじっていたのだが、高嶺自身、和端と仲がいいとは思っていなかった。
和端の家は両親そろっていて、ひとりっ子だ。甘えたい放題甘えて育ったのだろう、と高嶺は彼の母親と顔を合わせるたびに思っていた。
仲のいい親子で、ごく自然に会話をしている姿を見て、高嶺は戸惑いと驚きを感じた。高嶺の家にはないものだった。
こんな家庭に生まれていれば、もっと違う生活が出来たのだと思うと、歯がゆくなったこともある。最終的には諦めるしかない感情だった。どう足掻いても、高嶺は宮野家の子供にはなれなかった。
和端が羨ましくて、憎たらしくなったことはいくらでもある。
自分よりもずっと幸せで、悩みが少なくて、だから時々苛めたくなる。
そうじゃない、と高嶺は自分に言って、意識の中を漂った。
そんなものを見るためにここに来たわけではない。
肉体はないのに、何かが身体に絡みついた。
液体のような固体だった。まるでゼリーのように柔らかい。
<コロセ>
声が聞こえた。
<憎ラシイモノはコロセ>
高嶺は左右に首を振った。違う、と心の中で叫ぶ。
和端のことは嫌いじゃない。
過去の記憶があった。生まれる以前の姿。
氷室高嶺になる以前の、姿。
高嶺の意識は驚いたように止まった。
忘れていたモノが蘇った。
そこには真実が横たわっており、高嶺はここへ来たことを後悔した。
(罠だ)
身体に絡みついた生き物が、少しずつ高嶺を浸食した。気づいた高嶺は必死で抵抗したが、魅魔を通じて魏魔の意識が高嶺を飲み込もうとしている。
(嫌だ!)
魏魔に浸食された高嶺は、必死で喘いでも自分の意思では動けなくなった。このまま殀愧に操られてしまうのかと思うと、悔しくてたまらなかった。
隙をつかれたのだ。
いろいろなものを見せられて、高嶺の精神が弱ったところをつかれたのだ。
魏魔に操られた高嶺は、意識の底で凝縮されているエネルギーをつかんだ。
光が散った。
まばゆい閃光が、辺りにはじける。
高嶺の意識は、そのまま、消えた。
「高嶺!」
ゆらりと半身を起こし、ぼんやりと瞼を開いた高嶺を、和端は心配そうに見守っていた。
高嶺の目は、焦点がなかなか合わず、ここで何をしていたのかすら思い出せないような気配だった。
「高嶺?」
和端は不安になって、高嶺の両肩をつかんで軽くゆさぶる。
目が合った。
ゾクリ、と和端の背筋が冷えた。
(高嶺の目じゃない)
直感だった。
だが、そんなはずはない。
「……高嶺? どうした?」
どうすればいいのかわからぬまま、和端は再び声をかける。
高嶺は返事すらせず、和端は困ったように弥帋を見た。
「あの、高嶺、なんか変ですよ」
「いや、大丈夫だろう。きみの場合よりもショックが大きかったようだね。しばらく時間を置けば平気だろう」
和端は戸惑いながら、ぼんやりしたままの高嶺を見つめた。
「本当……ですか?」
半信半疑の和端に向かって頷いて、弥帋は帰る仕度をはじめた。
「力を得ることにはひとまず成功した。これで僕がいなくてもきみたちは大丈夫だ」
「えっ」
和端が心底から驚く。
「ちょっと待ってくださいよっ。何をどうするのか全然知らないんですけどっ」
「訓練などなくても、きみたちなら使える力だ。忘れていてもいざとなれば身体が勝手に動く」
それだけ言い残すと、弥帋は玄関から出て行った。
和端は茫然とたたずみ、しばらく言葉もなかった。
「……そういうのって、ちょっと無責任なんじゃない?」
ため息つきつつ呟いて、和端は傍らに座っている高嶺の方へと視線を移した。
高嶺は、ゆっくりと目をあげた。
目の前には和端が立っている。
彼にとって厭わしい能力が身についていた。
けれど大丈夫だ。
高嶺にも同等の力が宿っている。
「……むかしの」
「え?」
突然喋り出した高嶺に驚いて、和端が素頓狂な声をあげた。
「むかしの記憶を見なかったか」
「よかった。高嶺、元に戻ったんだ?」
和端が笑顔を浮かべかけた。
「見なかったか」
だがその笑顔はすぐに消えた。
高嶺の様子は尋常ではなかった。
和端の腕をつかみ、高嶺はゆっくりと立ち上がる。
「見ただろう」
「み……、見たかもしれないけど、もう覚えてない」
「そうか」
高嶺が笑った。まがまがしい笑みだった。
和端が思わず身を引く。
「高嶺……?」
「ラーヴァの生き残りは五人いる。あの状況で、よく絶滅せずに済んだものだ。だがもう、それも終わる」
「……なに?」
意味がわからず、和端は眉をひそめる。
ガシャーン! とガラスの砕ける音が響いた。和端は驚いて、窓の方へと視線を走らせる。
ベランダから、見覚えのある魅魔が入って来た。和端はつかまれている腕を振り払おうとしたが、尋常ではない力が高嶺の手には働いていた。
「高嶺っ、しっかりしろよっ! ヤバイってば!!」
「考えを変えた。残りすくないラーヴァであるからこそ、我が喰らうことにした。力のある者こそ統括者となれる。殀愧の王になるのだ。幸い、ここにはラーヴァの生き残りが二人いる」
魅魔は美しい顔に壮絶な悪魔の笑みを浮かべて和端に近寄ってきた。
「じょ……冗談じゃないっ。喰われてたまるかよっ」
和端は慌てて左右を見渡した。しかし高嶺は腕だけでなく、逃がすまいと和端の肩までしっかりとつかむ。
「高嶺ぇっ。なんでこいつに協力してんだよっ!」
「ラムダの内部には魏魔が棲んでいる。今は我の奴隷だ。思ったよりもたやすかったな」
ラムダ、という単語の意味するところはわからなかったが、今の言葉が高嶺を指しているのは理解した。
「てめっ、高嶺に何したっ」
和端が噛みつく勢いで叫んだ。
魅魔はフッと笑む。
「まだ何も。操っているだけだ。魏魔を使って」
「なにぃっ」
魏魔を使ってどうやって操ってるのか、和端には見当もつかない。しかし、この魅魔のせいで高嶺の様子がおかしいことだけはわかった。
弥帋の言っていた、引き出した能力がどうすれば使えるのか。和端はぐるぐると思考をめぐらせたが、答えなど見つからなかった。
「っかんねーよっ!! ちくしょ、高嶺っ、離せっ!」
じたばたと暴れるが、高嶺の力は意外に強かった。魅魔は和端の目の前で立ち止まり、嘲るような見下すような目で見やった。
「我々魅魔は、他の殀愧のように意地汚ない喰らい方はせぬ。魏魔も眩魔も魂だけでなく喰った肉とも融合する。だが我々は魂しか喰わぬ」
「喰う喰うって、うっせーなっ!!」
恐怖感は当然あるのだが、強がらなくては対抗できそうになかった。
ムリヤリ気力を奮い立たせる。
「高嶺っ、俺のことわかれよなっ」
和端をとらえて離さない高嶺には、表情というものがまったくない。
魅魔の右手があがった。和端の額の位置に。
思わず身を引いた和端を追うように、手が迫った。
ニヤリと魅魔が笑む。
「なるほど、力は得たが、方法を知らぬか」
和端は弥帋を呪った。なにが殀愧と戦える力だ。
(使い方がわからなくっちゃ、どうにもならないじゃんかっ)
魅魔の掌が、和端の額に触れる。
刹那、目の前で光がはじけたような感覚が降る。
「うわっ」
幻覚が、襲ってきた。
額に魅魔の手がめりこみ、脳をかきまわされるような幻覚。
「うわああっ」
身体がえぐられるような嫌悪感。
バチッと火花が散った。身体の内部で。
散ったように感じただけかもしれない。
身を縮ませる和端の内部から、光が膨張する。その光は身体の外へと広がり、魅魔の目を焼いた。光はさらに大きくなり、部屋いっぱいに広がった。
高嶺の腕が離れた。眩しさに目をかばっている。
和端の身体がよろめいて、ベランダの方へと向かった。手すりへと近寄ると、何かに引きずられるようにベランダから落ちた。