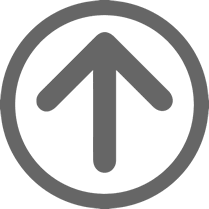(執筆日:2009年08月09日)
森の中を歩いている時間はとても長かった。
歩いても歩いても終わることのない森。
普段バスケをやっていて、よかったとしみじみ思う。
思いがけないところで、培った体力が役に立った。
さすがに疲れてきたのか、各務くんが静かになる。私も喋る気にはなれなくなった。
先を歩くオルドの背中を追うように、ただひたすら足を動かし続ける。
鬱蒼と繁る木々が少しずつ減ってきた。空から降る陽射しの眩しさが強まってくる。
明るい。森の終わりが近づいてきたことを示している気がした。
「もうすぐだ」
オルドが振り返り、唐突に口を開いた。
さらに私たち三人は歩く。歩く。歩く。
だいぶ疲れてきた頃、森が終わった。
足元に道らしき道。でもアスファルトじゃない。土の道。
砂利がごろごろしてる、整備されていない道。
森の終わりと同時に見える、辺りの光景。
まるでどこかの外国。日本とはまるで違う、見たことのない景色。
広大で、壮大な、一面の草原。
草原を割るように、一本の土の道が延々と遠くまで続いている。
とたんに蘇るホームシック。帰りたい。日本に帰りたい。家に帰りたい。
ギュッと各務くんの手を握った。ずっとつないだままだった手。不安で怖かったから、握った。
各務くんが無言で振り向いた。何も言わない。
何も言わない代わりに、手を握り返してくれた。
さらに道は続く。私たち三人はひたすら歩いた。
どれだけの時間、歩いていたんだろう。ようやく終わりが見えた。
高い塀に囲まれた小さな町が視界に飛び込んでくる。
出入り口には鎧に包まれた兵士らしき人物が二人。微動だにせず立っていた。
厳粛な空気に、軽く鳥肌が立つ。馴染みのないものに対する畏怖だった。