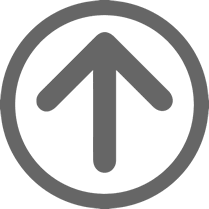(初出:不明 執筆日:1996年10月09日)
視線を感じてぼくは足を止めた。
電車はちょうど今、ホームに入ってきて目の前で止まる。ドアが開いて流れるように大勢の人達が出てきて、ぼくは慌てて避けた。ぼくは列の先頭にいたから、後ろの人達が迷惑そうにぼくを避けて電車に乗り込んでいく。
ぼくがまだ乗っていないのに、電車はあっさりとドアを閉めて発車して行ってしまった。
だけどぼくはもう、電車なんてどうでもよかった。
視線を感じて振り返った先には、ひとりの小さな女の子が立っていた。彼女の周りに保護者らしき人はいない。その上、彼女の着ている服はふわふわのドレスのようなワンピースで、日常そこらで見かけるには不釣り合いな感じがした。
年齢はだいたい、小学校一年生くらいだろうか。
ぼくと目が合うと少女はにっこりと笑った。ぼくはどう反応したらいいのかわからなくて、正直困っていた。
少女がとことことぼくの方に向かって走り、唖然としているぼくの右手をつかんで走ろうとする。
「こっち、こっち」
「えっ? あのっ、ちょっとっ」
唐突な行動にぼくは慌てた。華奢でかわいらしい女の子は予想もしない力を発揮して、ぼくをひっぱって走った。階段を駆けあがり、改札をくぐろうとする。少女の手には切符があり、自動改札に差し込んだ。ぼくも慌てて定期をとりだし、自動改札を出ようとした。
その瞬間だった。
ぼくの周囲がいきなり乳白色になり、異質な空間に入ってしまったような奇妙な違和感を感じたのは。
一瞬後には、普通の光景だった。ぼくは無事に改札を出ており、目の前にはやはり何者なのかわからない少女がぼくを見て笑っていた。
「ようこそ」
見知らぬ女の子はぼくに向かってはっきりそう言った。
わけがわからなくてぼくは、少し苛立ちはじめた。目の前の少女がいくら年端がいかなくても、ぼくはこれから学校に行かなくてはならないのだし、子供の遊びに付き合ってる暇なんかなかった。
「きみ、どこの子? 名前は?」
「かずや」
「……っ!」
ぼくはびっくりした。和哉はぼくの名前だ。
ぼくが絶句していると、少女はまたぼくの手を取って走ろうとした。
「かずや、行こ」
「……ちょっ……待ってよ!」
少女は名乗らないつもりらしい。だけどなんでぼくの名前を知っているんだ?
ぼくはますます混乱して、少女にひっぱられるまま走ってしまった。
駅前の光景はぼくの知っているもののはずだった。
なのになんでぼくは違和感を覚えているのだろう。
「きみさ、いったいぼくをどこに連れていくつもりなんだい?」
少し怒ったフリして訊いてみたが、少女は屈託なく笑っただけだった。
「こっちだよ」
少女はまたぼくの手をひっぱって、走る。つられるままぼくも走ったが、ふとぼくの視線が駅前の周辺に向かった。
また違和感だ。
いつもとなんら変わらないように見えるのに、この背筋が寒くなるような違和感は何だ?
「ねえ、本当にどこに連れていく気だよっ」
走りながら少女に訊いた。ぼくの不安の種はこの子でもある。なんでこんなに小さな子供が、こんなに早く走るんだろう。息を切らしている様子もない。
しばらく走ると、少女はひとつの建物の前で止まった。
「ここ」
指を差すので見上げると、そこは単なる喫茶店のようだった。見覚えはない。
「喉、かわいたの?」
少女に訊いてみたが、返事はなかった。
ただしきりに入れと促すので、しぶしぶぼくはドアをくぐる。
中に入った瞬間、妙な重力を感じた。でもそれはやっぱり一瞬のことで、単にぼくが神経質になってただけなんじゃないかとも思えた。
振り返ると少女の姿はすでになかった。
ぼくは舌を打つ。
「逃げたな」
からかわれたのだと思って、ぼくは腹が立った。
「いらっしゃいませ」
ウェイターらしき中年の男がぼくに向かって言うので、仕方なく席についた。これで学校は完全に遅刻だ。なんだかどうでもよくなってきた。
「ご注文は」
水の入ったグラスをテーブルに置きながらウェイターが言うので、ぼくは「コーヒー」と答えた。待っている間、ぼくは無造作に店内を眺めていた。
また奇妙な感覚がぼくを捉えた。
店内には何人かの客がいる。だが、どれもこれも仮装行列のような変な恰好だ。妙なところに入りこんでしまったな、と思っていると、カランと音がして新たな客が入ってきた。
その客をなんとなく見たぼくは、次の瞬間に愕然とする。
客の顔はぼくだった。しかも、同じ制服を着ている。
もうひとりのぼくは、ぼくを見つけると躊躇なく目の前の席に腰をおろした。驚いた様子もない。
「こんにちは」
「……」
ぼくは鼓動が早くなるのを抑えられない。冷や汗までが全身に噴き出す。
これは……ぼくだ。どう見ても。ぼくには双子なんていないから、この世に同じ顔なんていないはずだ。なのに。
もうひとりのぼくは落ち着きはらっていた。ウェイターが注文を聞きに来ると、ぼくと同じように「コーヒー」と言った。
「そんなに怖がらないで」
と、ぼくに言われても、困る。
「……おまえ、誰だ」
勇気をふりしぼって、ぼくは訊いた。すると相手は愛想よく笑い、ぬけぬけと答えた。
「ぼくはきみだよ。そしてきみはぼくだ。違うかい?」
……違わなかった。
ここにいるのは確かにぼくだ。だが完全にぼくじゃない。
だって本当のぼくはここにいる。ぼくがもうひとりいるはずがない。
「自分とこうして対話できるなんて、ぼくは嬉しいよ。これで言いたいことがきみに言える」
ぼくは不安と恐怖の両方にさいなまれながら、相手が笑いながら喋っているのをじっと聞いていた。本当はここから逃げ出してしまいたい。なのに、身体はまるで椅子に貼りついてしまったみたいに動かない。
「人間の心の中にはもうひとりの自分がいるって知ってた?」
ぼくは左右に首を振る。
「ぼくはいつでもきみを見ていた。監視していた、という方が正しいかな? ぼくはいつもきみの潜在意識の中で生きている。きみの行動も言葉もみんな聞いてるし、本音も建て前も全部知ってる。他人に知られたくないような秘密も知ってる。……なんて顔だよ。そんなにぼくが怖いかい? 今回ぼくは機会に恵まれた。ぼくはきみだけれど、正確に言うときみとは少し違う。ぼくはきみがいつもやりたくても出来なかったことを実行する力持ってる。きみはどちらかとと言うと内向的で、言いたいことすべて言えるタイプじゃないよね。学校でも家でも、押しつぶされそうになりながら生きてる。萎縮してしまってる。なまじ成績がいいから、期待までされてる。きみは健気にも期待に応えようという努力もしている。だから余計に苦しくなってるんだろう? 時々心の中で悲鳴をあげているのをぼくは知っている」
「……だから、なんだよ」
「きみを、解放してあげたいんだ」
「……」
容易に信じられるような話じゃなかった。
目の前にぼくとそっくりな、ぼくとは違う人間がいることにも戸惑いをなくせないのに、こんな話信じる方がどうかしてた。
「ぼくと同じ顔で同じ声だけど、おまえ、ぼくじゃない。確かに時々苦しいけど、逃げようと思ってたわけじゃないし、それなりに毎日過ごしてる。友達だっているし、まったく自由がないわけでもないし、母さんや父さんのことだった好きだし……っ」
「そう。きみのそういうところが、ずっときみを頑張らせてきたんだ。だけど一緒に生きているぼくにしてみれば、苦痛さ。せっかくこうしてきみと出会えたんだ。ぼくの望みをかなえさせてもらうよ」
目の前でフラッシュが起こった。ぼくは慌てて腕で目をかばった。光の向こうで、もうひとりのぼくが笑ったのを……ぼくは見た。
ぼくは学校にいた。
周りを見ると、まだ授業が始まってないらしく、それぞれが好きなように過ごしている。
ぼくは何度か瞬いて、軽く左右に首を振った。
……どうやら夢を見ていたらしい。
おかしな夢だった。
「和哉、どーしたんだ? ボケッとして」
「ああ、寝不足なんだ、実は」
友達に声をかけられて、ぼくは答えている。……ちょっと待て。
今のはぼくが言ったんじゃない。
ぼくの身体が勝手に立ち上がった。
「かったるいから、授業さぼるよ。適当にごまかしといて」
そう言いながら、ぼくは教室を出ていた。
……変だ。
これはぼくじゃない。
ぼくはそんなことを言わない。
まさか。
ぼくは気がついた。
これは潜在意識の奥でぼくを監視していたという、もうひとりのぼくだ。
そしてぼくはもうひとつ気づく。
こいつはもしかすると、ぼくと正反対の性質をしているんじゃないか?
途中で他のクラスの女子生徒と肩がぶつかった。刹那、ぼくは彼女を殴っていた。
「ちょっとぉっ、なにすんのよ、あんたっ!」
殴られた女子生徒と一緒にいた娘が、文句を言う。それをぼくは心底から蔑むような目で見据え、相手をおびえさせた。
ぼくじゃない。
こんなのはぼくじゃない。
「ちょっとここで派手なことしてみないか?」
まるでぼくに聞かせるように、そいつが言った。
END