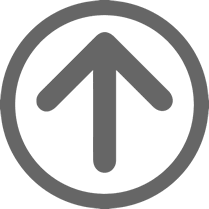(執筆日:2008年07月31日)
「あーでも、喋ったらなんか楽になった。やっぱりこういうのは一人で溜め込んじゃダメなんだね」
津王の声が急に明るくなり、すっきりした響きを漂わせ始めた。
僕は津王の横で立ち上がった。
「元気になったみたいだから、帰るよ」
「あ、うん。つきあってくれて、ありがとーっ」
元気よく手を振られてしまった。
僕は苦笑しつつ自転車に乗り、そのまま敢えて一度も振り向かずに走り去った。
ちょっとぐらいは振り向いてやったほうがよかったかな。
なんて考えもなくはなかったけど、二人の距離がますます縮まりそうな気がしたからやめた。
他人の寿命が見えるというのは、決して文字や数字で見えるというわけじゃない。
相手を見た瞬間に、脳にイメージが飛び込んでくる。そして何月何日の何時何分に、その命が消えるのかっていうのが全てわかってしまう。
ただ、何が原因で命を落とすのかまではわからない。
その命が消えてなくなる。
僕にわかるのはそれだけだ。
幼い頃から僕は、ペットを飼うのを非常に嫌がった。父親と母親が、行きたくない僕をムリヤリ家から連れ出して、ペットショップへと向かったことがある。耐えられなかった。ショーケースの中にいる犬や猫が、いつまで生きられるのかすべて見えてしまう。確実に僕より短い命。いつ死ぬのかわかっているのに、愛情を注ぐなんてつらい行為は、僕には耐えられなかった。
泣いて嫌がった結果、うちでペットが飼われたことは今まで一度もない。
親からは「変わった子」という烙印は押されてしまったけど、後悔はしてない。
自分を守るためなんだ。僕はそうすることでしか自分を守れない。
もうすぐ死ぬ相手に、情は移さない。
だから僕は、津王とは距離を置かなきゃいけない。
近づいてしまったら、結果的につらくなるのは僕のほうだ。
そう思っているのに。
家に帰って携帯電話を眺めてみると、津王からメールが来ていた。
……?
アドレス教えた覚えないんだけど。
『さっきはありがとね!俺復活したよ!』
内容はそれだけだった。
僕は返信せず、携帯電話を勉強机の上へと置いた。