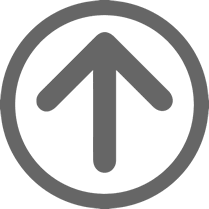(執筆日:1998年04月12日)
バイト先で二度も倒れてしまい、強制的に帰らされた。
高嶺は苦い気持ちで帰途を歩いている。いつもの時間よりも早く、辺りはまだ明るい。
学生ではない高嶺は、主にバイトは昼間行く。帰りに病院へ寄って行った方がいいと言われたものの、高嶺は家に帰る道を歩いていた。病院へ行ったところでなんとかなるような病気や怪我とは違う。
原因ははっきりとわかっていた。体内に魏魔がいるせいだ。それで体調のバランスが崩れているのだ。
その程度で終わるのなら、まだいい。だが、これから身体や精神にどのような影響があるのか。なにしろ今の高嶺は尋常な状態ではない。
弥帋の顔が脳裏に浮かんだ。
言うべきか、言わないでおくか。高嶺はまだ弥帋が信用できない。
だが、このままひとりで抱え込んでいて解決する問題ではない。
「……ったく、迷惑だな」
運が悪いとしか言いようがなかった。数多くいる人間の中で、たまたま高嶺がターゲットにされてしまったのだ。行方不明になった雪乃のように。
それでもまだ、和端が犠牲にならなかっただけでもいいと思っていた。決して自分が背負い込みたかったわけではないが、和端がそんな目に遭うのを見るのは嫌だった。
マンションに戻ると、和端と弥帋がいた。
まだいたのか、と言いたそうな高嶺の顔を見て、弥帋が穏やかな口調で「おかえり」と言った。
ふたりは居間で何か話をしていたようだ。テレビすら消してある。和端が家にいてテレビが消えているのは非常に珍しい。
和端が様子を探るような目をして寄ってくる。
「高嶺、ずいぶん早かったね」
「暇になったから帰れってさ」
「へー」
和端は素直に信じなかった。今朝よりも顔色の悪くなっている高嶺をじっと見やる。
「高嶺、顔色最悪だよ? ホントは具合悪くて帰されたんじゃないの?」
「違う」
高嶺は視線をそらして洗濯機の方へと向かった。和端は妙なところで鋭いから、あまり傍にいると詮索されてしまう。
たまっている洗濯物を洗いながら、高嶺は台所の片付けをはじめた。そうすることで、和端から離れていた。
ふと目を向けると、和端は弥帋と何やら熱心に話をしている。その内容は高嶺の耳には届かなかった。
片付けが終わった後は、掃除をはじめた。そこでようやく気がついたように和端が声をかけてくる。
「高嶺、具合い悪いんなら、部屋で休んでた方がいいよ? さらに顔色悪くなってんだけど」
確かに身体はだるい。しかしそんなに顔色が悪いとは思えず、高嶺は鏡を見た。疲労感の強い、病人のような顔色だった。
「ね、最悪だろ? 寝てなよ」
和端に強引に部屋に押し込められて、ベッドに寝かされた。
だが高嶺は不安だった。動いて何かしていないと気が休まらない。眠ってしまったら、その間に身体が乗っ取られるかもしれない。
結局、和端が部屋を出て行くなり起き上がって、高嶺は自分の部屋の片付けをはじめた。
「たかねってばっ!」
物音が居間まで届いていたらしく、和端が飛び込んで来た。顔を見ると、なにやら怒っている。
「なに怒ってんだよ、おまえ」
「寝てろって言っただろっ。今にも倒れそうな顔でさっ。それとも一緒に病院行く? ちょうど弥帋さんいるし、車もあるからムリヤリにでも連れて行けるけどっ? だいたい、なんで急にそんな……」
怒鳴っていた和端の声が唐突にとぎれた。
「もしかして、ゆうべ、なんかあった?」
静かに重い口調で、和端が問いかけた。
高嶺は軽く舌打ちし、面倒臭そうに前髪をかきあげた。高嶺がごまかそうと口を開きかけたところで、和端の背後から弥帋が顔を出した。
「取り込み中のところ悪いけれど、ちょっといいかい?」
「……なんですか」
刺のある声で高嶺が答える。自分でも何故これほどまで弥帋を厭いたくなるのかわからなかった。
「先程、僕は和端くんに能力の引き出し方を教えていたんだが……」
「能力の引き出し方?」
弥帋がいったい何を言い出したのか、わけがわからず高嶺が怪訝そうに眉をひそめた。
澄ました態度で弥帋が話を続ける。
「そう。きみたちには不思議なことに、殀愧と戦うだけの能力が眠っている」
「……なんでそんなこと、わかるんですか」
いくらなんでも信じられるような話ではない。胡散臭さが漂うだけだ。
「僕がそうだからね。同じ種類の人間を見分けることくらいできる。昨日見せただろう、僕の持つ能力を。きみたち二人は、僕よりも能力が強そうなんだ。試してみようとは思わないかい? このまま黙って殺される日を待つのも嫌だろう?」
「殺されるとは限りませんけど」
「きみたちが殀愧と戦えるだけの能力を目覚めさせれば、生き延びられる可能性が高くなる」
「あんた、SFの読みすぎなんじゃないですか」
「高嶺!」
慌てたように和端が呼ぶ。しかし高嶺は弥帋を睨み続けたままだし、弥帋は穏やかに澄ましたままだった。
「殀愧の存在をその目で確かめたばかりだというのに、まだそんなことを言うのかい? 現実主義なのはいいけれどね、実際に見たものをなかったことには出来ないだろう。第一きみは実際に殺されかけたことがある。あの時、僕が助けなければ今ここに立っていることすらできないんだ。それに、僕は戦う能力を持っていない者に、さも使えるような話は持ちかけたりしない。初めて会った時からわかるんだよ。能力のある者とない者くらいの区別はね」
高嶺はゆっくりと和端の方へ視線を向けた。
「で、おまえは使えたわけ? そのチカラってやつ」
「半日かそこらで出来るわけないだろ?」
「ほらね」
馬鹿にしたように高嶺が笑った。
「普通の人間にそんな力があるなら、今ごろ殀愧と戦える連中は山のようにいるさ。なのにどこにもそんな奴はいないし、行方不明者は増えてる。たまたまあんたにはそういう能力があるかもしれないけど、誰もかれも使えると思われちゃ迷惑だな」
「先程言った通り、可能性のない者にこんな話はしない。そんなふうに頭から否定する前に、試してみようとは思わないのかい? それとも殀愧に喰われたいのか」
本当にそんな能力が眠っているなら、昨夜だって体内に殀愧が入り込んだり出来なかったはずだ。高嶺はそう思ったが、口にはしなかった。
「高嶺」
傍にいる和端が呼びかけた。
「俺さ、思ったんだけど、やんないうちに諦めんの、よくないことじゃない? 高嶺ってそういうとこあるよね。なにもしてないうちに頭だけで考えて、無理だって決めつけんの。そんなだからいつまで経っても、家族と理解しあえないんじゃない?」
「それとこれとは関係ないだろ」
「一緒だよ。高嶺ってあんまり努力とかしないじゃん。俺もしないけどさ。高嶺って恋愛に対しても適当だし、根本的なとこで人間信用してないじゃん。それにこのまま黙って狙われんの待ってるのとか嫌だろ? そんな簡単に死にたくないだろ? 行方不明になって新聞とかニュースになるの、嫌だろ? だからさ、ここは一度、弥帋さん信じてみない? 俺も一緒なんだしさ」
和端の言葉を聞いているうちに、高嶺の考えが揺らいだ。それを邪魔するかのように、身体の奥が痛みを覚える。
いま、はっきりとわかった。これほどまで弥帋を厭う理由が。
身体の中の殀愧が、弥帋を拒絶しているのだ。
「い、て……」
「高嶺?」
急に胸を押さえてうずくまった高嶺に、和端が驚いた声を出す。
「どしたの?」
高嶺は答えられなかった。身体だけではない、頭の中まで痛みが走る。思考が働かなかった。まだ日は暮れていないのに。
痛みに必死で耐えながら、高嶺は弥帋の顔を見た。もしかすれば、体内に魏魔が入り込んでいることを見抜くかもしれない。そうしたら。
魏魔を追い出す方法がなかったとしたら、高嶺が排除されるかもしれない。
だが弥帋は、驚いた表情を浮かべただけで、何か言っている。高嶺の耳は正常に働かなくなったようで、声が聞こえなかった。
唐突に意識が消え、高嶺は床に倒れ込んだ。
目を覚ました時、高嶺はまだ自分の意識が残っていることを知って安堵した。
枕元の時計を見た。すでに夜の八時半を過ぎていた。
長い時間、意識がなかったようだ。高嶺はベッドの上で半身を起こしてみたが、痛みもだるさも消えていた。
この時刻なら、和端はきっと店屋物でも取って食べただろう。そんなふうに思いながら、高嶺はゆっくりと部屋から出た。身体もまだ自分のものだった。
「高嶺っ!」
部屋から顔を出すなり、和端が声をあげた。慌てて飛んで来る。
「起きて大丈夫? まだ寝てていいんだよ。どっか痛いとこは?」
立て続けに言葉が襲いかかり、高嶺は少々クラクラした。
「……いや、平気」
居間の椅子を見ると、弥帋がいた。その表情を見る限り、高嶺の内部に魏魔がいることはまだ気づいていないようだ。
弥帋の能力がその程度で、よかったのか悪かったのか、高嶺には判断できなかった。
身体中の神経に魏魔が張りついているような感覚は、やはり消えない。だからもう、高嶺は諦めていた。魏魔をこの身体から剥がすのは無理だろう。
それでも乗っ取られないために足掻くつもりではいた。どれほど足掻いても駄目なら、そのとき自分の命を断つしかなかった。
高嶺はふらつく足取りで弥帋の前まで来ると、じっと見据えた。
「さっきの話だけど、その能力とかいうの引き出せば確実に殀愧に勝てるか?」
再び身体の奥が痛みだした。それでも高嶺は屈しなかった。
弥帋は感情の起伏のない穏やかさで、静かに頷いた。
「もちろん。ただし、苛烈な戦いになることは確かだろうがね」
「なんでもいい。勝てれば」
身体の中で魏魔が抵抗していた。高嶺の口から出た言葉を否定させたいようだった。
高嶺は歯をくいしばり、脳にまで浸透してくる魏魔の触手を完全に無視する。
魏魔はまだ、高嶺の意識を奪えない。そのことがはっきりとしただけでもよかった。まだ高嶺は自分の意思で動ける。
「でも高嶺、今はまずいよ。ふらふらだし」
「早い方がいい。できるだけ」
どこまで自分の精神が持つのかわからない今、なるべく早いうちに殀愧と戦う力を得た方がいい。
「わかった」
弥帋がうっすらと微笑んだ。その笑みを見た瞬間に、高嶺は罠に陥ったような気がしたが、気のせいだと片付けた。今は弥帋しか頼れる人物がいないのだ。
「ふたりとも目を閉じてくれ」
弥帋の声が静まり返った部屋の中で響く。
言われた通り瞼を閉ざした高嶺と和端は、深く椅子に腰掛けていた。
弥帋の声は妙に心地よく、催眠術にでもかかっているような気分になる。
「私の声をよく聞くんだ。きみたちふたりはこの声をよく知っている。遥か昔、とてもよく聞いた声だ。きみたちの魂の奥には眠り続けている力がある。この世に生まれ直した際に封印した力だ。いま、その力を解放する時が来た。殀愧がこの世界にまで追って来たからには、力は解放されねばならない。力の使い方はよく知っているだろう。二年前と同じように使えばいい。その時の記憶はなくとも、潜在意識がすべて覚えていてくれている。私の声はきっかけにすぎない。力の解放はきみたち自身が行なわねばできない。自己をよく見つめることだ。深い……深い場所に、きみたちの力が在る。少し手を伸ばせばたやすく届く場所に」
高嶺と和端の意識は半覚醒状態に陥っていた。弥帋の声は確かに催眠状態を引き起こしていた。言われるままに高嶺と和端は自分の内部を見つめていた。言葉の内容に対して疑問は覚えなかった。
精神世界の奥底……忘れられた記憶の破片が残されている場所へ。
奇妙な浮遊感の中で、和端は意識を下へ下へと運んだ。忘れていたかつての記憶があふれていた。そこには昔の自分がいた。自分の正体を初めて知った。意識の底にはエネルギーの塊が凝縮されて沈んでいる。和端は手を伸ばした。弥帋の言う通りたやすかった。こんなに簡単ならもっと早くやればよかった……と思った瞬間に、急激に意識が浮上する。
「……あ、れ」
ビクッと身体が揺れて、和端は瞬きを繰り返した。あまりにも唐突で、何が起こったのかわからない。目の前には弥帋が立っていた。彼の視線は和端になく、高嶺を見つめている。
何かたくさんのものを見た気がするのに、和端はすべてを忘れてしまった。椅子に腰掛ける前の記憶しか残っていない。まるで朝起きたら見た夢すべてを忘れてしまったような感覚だった。
何度か掌を握ったり開いたりして、自分が起きていることを確認した。それからゆっくりと高嶺の方へ視線を向ける。
和端は目を瞠った。
高嶺は椅子に腰掛けたまま身体をふたつに折り曲げている。苦痛を感じているようで、脂汗が額から流れて落ちる。眉根を寄せて歯を食いしばっていた。
「た……高嶺?」
和端はあっけないほど簡単に事が済んでしまったというのに、高嶺はそうではないらしい。
「う……ああっ」
胸をかきむしるような仕種をして、苦痛の声を洩らす。和端はオロオロと弥帋を見るが、彼は高嶺に真剣な眼差しを注いだままで何の反応もない。
「高嶺、高嶺」
やめさせようと和端は高嶺の肩をつかみ、軽く揺さぶった。これほど苦痛を感じるなら、即座にやめさせなくては高嶺が危ないと思った。
「もういいよ。やめろよ、高嶺」
「止めないでくれ、和端くん」
弥帋の冷徹な声が降りそそいだ。和端は思わず弥帋を睨みつけた。
「だってこのままじゃ高嶺がっ」
「大丈夫だ。この程度のことで死にはしない」
「死ななかったとしても、高嶺が壊れるかもしれないだろっ」
「こんなことで壊れる程度の精神力ではとうてい殀愧たちとは戦えない。何度も言ったはずだ。殀愧との戦いは苛烈だと」
「だけどっ」
和端は激しく当惑しながらも、手も足も出せなかった。今すぐ高嶺の意識をこちら側に戻したいのだが、下手に扱えば危険が起こるかもしれない。だからこそ弥帋に止めてもらいたかったのだが、それは無理そうである。高嶺は苦痛に身をよじりながら、まるで体内で何かと格闘しているように喉の奥から悲鳴をあげる。かろうじて、椅子から転げ落ちるようなことはなかった。