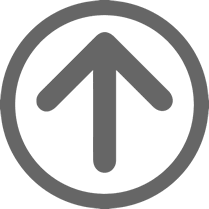(執筆日:1998年02月26日)
高嶺がマンションに帰ると、和端はテレビを見て笑っていた。
バイト帰りのついでに買い物してきた高嶺は、それらを冷蔵庫にしまったり棚に置いたりしながら、声をかけた。
「部屋、ちっとはなんとかしたか?」
「ちょっとだけねー」
居間で返事をする和端の声は明るかった。高嶺はひょいと居間へ顔を覗かせて、険しい声を出した。
「おまえさ、一応言っとくけど、夜ぜったい外に出んなよ。今日俺が言ったこと、ホントのホントに本当のことなんだからな。信じる信じないはおまえの勝手だけど」
「うん、わかってるって」
「……ったく、返事だけなんだからな」
ぼやきながら高嶺は、夕飯の支度をはじめた。和端はテレビから視線をはずし、台所の方を見やる。小さなため息を洩らして、ベランダの窓を見た。今はカーテンが閉ざされている。
あれから急いで慌ててガラス屋に連絡し、修復してもらった。このまま黙っていれば、高嶺が気がつくことはないだろう。
余計な心配や不安を感じさせたくない、という気持ちもあったが、和端自身あれは夢か何かだったと思い込みたかった。
昨日の夜中に高嶺が狙われたのも、単なる偶然であってほしかった。
(見つけたぞ)
思い出して、ザワッと寒気が走る。得体の知れない不安がよぎる。
高嶺は夜外に出るなと言うが、昼間とか夜とかは関係ないのではないだろうか。
そんな気がしてならない和端は落ち着かない。テレビを見て気を紛らわせてみているのだが。
「そーいや高嶺さー、今朝の人、あれって誰なの?」
「言っただろ、弥帋って奴だって」
うるさそうに高嶺が返事した。
「どういう知り合いなの?」
「偶然会ったっつったろ。もう忘れたのかよ」
「そうじゃなくってさぁ……」
高嶺は昨夜に会った怪物の正体をいろいろと聞いたのだ。だがそれを説明できる、弥帋という人はいったい何者なのか?
第一、ふつうの人間に、そんな状況の高嶺を助けられるはずがない。そんな冷静な行動などできない。
「ねえ、弥帋さんってどんな人?」
「てめえのメシ作ってんだぞ、邪魔するな」
「はぁい」
和端は椅子の上にちょこんと座って、黙ってテレビを見ることにした。
しばらくして、高嶺が夕飯をテーブルに並べはじめた。顔を見たことで、和端の疑問が抑えきれなくなる。
「ねえ高嶺、おまえ怖くないの? 変なのに出会っちゃったんでしょ? 怖い目に遭ったんでしょ? なんでそんなに普通なの?」
「……信じてなかったんじゃないのかよ」
心底から不思議そうに高嶺に言われて、和端は口ごもった。すねたような態度で、続ける。
「べつに、信じたわけじゃないけどさぁ。ただ高嶺って、面倒がってちゃんといろいろ説明してくんないからさ、俺も困っちゃうんだよね。でさ、弥帋さんって、いったいどの辺に住んでるの?」
「……さあ。忘れた」
一呼吸置いての台詞がこれである。
和端はがくーっと肩を落とした。
「あいつに何か訊きてぇことでもあんの? なんかさっきからずっと気にしてんじゃん」
和端の向かいの椅子に腰をおろして、高嶺が怪訝そうに問いかけた。
「高嶺から聞くより、弥帋さんから説明された方が理解できそうな気がするからさ」
「ふーん」
嫌味を込めた音声で、高嶺が返事をする。
「どうせ俺は信憑性がねえよ」
「そうじゃなくってぇ」
不機嫌に食事をとりはじめた高嶺に、和端は取り繕うような声を出した。
「もしかしたらさ、高嶺も聞いてない、もっと詳しい話とかあるかもしれないじゃん。なんかその人詳しいからさ」
「……信じてなかったんじゃないのかよ」
今度は訝しむ態度で言った。何かを探るような目で和端を見る。
和端は慌てて話題を変えようとした。
「だから信じてないってば。それよりさ、さっきテレビで面白いのやってたんだけど……」
「和端」
食事の場に沈黙が降りた。
高嶺はまっすぐ和端を睨んでいる。
「ごまかすな」
「……ごまかしてないよ」
そうは言ってみたものの、高嶺をだますことはできなかった。
「とりあえず、弥帋さんに会わせてよ。それから全部話すからさ」
「……わかった」
高嶺はしぶしぶ頷いて承知した。
高嶺は弥帋から電話番号をもらっていた。和端のことがなければ、一生使うことなどないと思っていた。手書きで記されたメモを和端に渡し、自分でかけろと告げる。
すぐに弥帋とは連絡が取れ、そちらに行くと言って切れた。それから二十分くらい経った頃、玄関の呼び鈴が鳴り響く。
隙のない恰好と雰囲気を身にまとい、弥帋がふたりの部屋に入った。
居間に向かい合わせに座って、和端は弥帋に切り出す。高嶺はすこし離れたところで立って見ていた。
「いきなりですけど、俺、変なのに会ったんです」
和端は真剣そのもので切り出す。対して弥帋はさほど表情を変えない。
初めてそんな話を聞いた高嶺は、わずかに眉をあげた。
弥帋が問いかける。
「変なものとは?」
「あの……なんて言ったらいいか、形は普通の人間なんです。だけど、暗い感じに綺麗な人で、雰囲気がすごく異様でした。怖い感じでした。その人が、いきなりそこのベランダの窓を叩いてて、俺が顔出したら何の力も入れてないのに掌だけでガラスを割ったんです。それで……見つけたって言ってました」
「きみを?」
「たぶん」
和端は頷いた。心もとない表情で、高嶺の方を見る。
高嶺は難しい顔で黙って聞いていた。
「見つけたのは俺だけじゃなくて、ラムダとシグマを見つけたとも言ってました。仲間はそれだけかって。……あと、遥か昔、俺と仲間だったって……」
「なるほど」
弥帋はやはり冷静だった。和端は一瞬、自分の言葉が通じなかったのではないかと疑った。それほど弥帋は淡々としている。
「で、正体はわかったんですか」
高嶺が弥帋に向かって問いかけた。まるで弥帋の知識の程度をはかろうとするような、つっけんどんさだった。
そんな高嶺の態度には頓着せず、弥帋は実にあっさりと答えを告げた。
「それは魅魔だな」
「みま?」
和端が鸚鵡返しに言う。
「そう、魅魔だ。高嶺くんは昨日聞いただろう。それらは殀愧と呼ばれ、この世界の生き物ではない。魏魔という明確な形を持たぬもの、眩魔という餌を吸収して進化したもの、魅魔という最大レベルの進化を遂げたもの。眩魔と魅魔は餌によって変化の生じ方が異なる。魅魔の元は魏魔だが、眩魔との違いは餌だ。栄養価の高い餌を取り込めば、美しい姿と賢い頭脳を得ることができる。ただしいずれも負の方向性を持っているために、その力を破壊や破滅や侵略などの方へ使う」
「……なんなんですか、それ」
和端は当惑した顔で訊く。
「なんでそんなモンが日本にいるんですか?」
弥帋は少し考えるそぶりを見せてから、ゆっくりと首を左右に振った。
「そこまではわからない」
「昨日あんたさ、夜間にしかそいつが徘徊しないって言ったよな。どういうことなんだよ」
高嶺が食ってかかった。弥帋は穏やかに彼を見てから、和端の方へと視線を戻す。
「魏魔と眩魔は確かに夜間にしか徘徊しない。だが、魅魔だけは違う」
「……」
「魅魔は格段に能力が高い。だから昼間行動しても何の支障もないんだ。その上で、超能力のような妙な力も使う。餌を喰うしか脳のない魏魔や眩魔などとは比べものにならないんだよ」
弥帋は落ち着き払った様子で告げた。しかし彼の語る内容はあまりにも現実的ではない。高嶺も和端も、あの得体の知れない生き物と出会ってなければ、弥帋を頭のおかしい奴だと思うことだろう。
「で、そいつが見つけたとか言ってたモンが何かわかんのか?」
高嶺はさらに食ってかかる物言いをする。
弥帋はさらりと彼を見て、言葉を続けた。
「和端くんが見つけたもののひとつであることには間違いはないと言うことだろう」
「なんで和端が狙われんだ」
「それはまだわからない」
「じゃあ、なんであんたはそんな化け物の存在に詳しいんだ」
「やめなよ、高嶺」
白熱しかける高嶺に、和端がなだめるように声をかけた。一瞬、我を忘れかけた高嶺は、その声で正気に返る。自分でも、なぜこんなに熱くなったのかわからなかった。
「でも」
和端の視線が弥帋へと移る。
「どうしてそんなに詳しいのか、知りたいのは確かです」
弥帋が困ったように微笑した。
「それがね、僕にもわからないんだよ」
「わからない?」
高嶺と和端が同時に声をあげる。
弥帋は姿勢を改め直して、和端の方へ視線を留めた。
「僕がまだ幼少の頃だったろうか。それまで僕はごく普通の子供として過ごしていた。ある夜のことだ。僕の夢枕に不思議な光景が見えた。事実夢だったのか現実だったのか、確かめる術はないがね。そこは今僕たちが暮らしている世界とはどこか違っていた。日本でもなければ地球でもないような。その世界で暮らす平和な種族がいた。彼らは穏やかで争い事を知らなかったが、優秀な頭脳を持ち合わせていた。そんな彼らの元に侵略してくる種族がいた。それが殀愧だ。……なぜ、僕がそんな夢を見なくてはならなかったのか、そこまでは知らない。だが、翌朝目が覚めたら、奇妙な力が使えるようになっていた」
「奇妙な力?」
「そう。例えばね」
弥帋はさりげなく右手をあげた。無造作に掌を上へ向けて、高嶺と和端の注目を受ける。やがてその掌の中に光のようなものが集まった。眩しさに高嶺と和端が顔をしかめると、弥帋は「失礼」と一言告げて目の前にあるコーヒーカップに掌をかざした。刹那、パシィッと鋭い音とともにカップが砕け散る。身を乗り出していた和端は慌ててのけぞった。
「な……な……、なんなんですか、今のっ」
和端がうわずった声で訊く。高嶺は驚きのあまり声が出ない。茫然としている。
弥帋は落ち着き払った様子で、和端を見、高嶺を見た。
「これが先程言った、奇妙な力だ。殀愧という存在を知った頃から、ずっとなくなることなく使える力だ。この力のおかげで、殀愧と遭遇しても助かってきた」
「……」
和端も高嶺も言葉がない。
部屋がシンと静まったので、和端が慌てて話をつなげた。
「あ、あの……、弥帋さんて、その……アヤギだっけ? それに、何度も出会ってるんですか?」
「まだ十回も出会っていないよ」
「二、三回会っても多いですよー……」
和端が泣きそうな声を出す。
「やだな。俺たちそんなのに巻き込まれたんですかぁ? 喰われちゃうんですか?」
「情けない声を出すな、和端」
高嶺がたしなめる。
「こいつと出会ってるだけマシだ、俺たちは。なんなのかわかんねぇまま喰われちまった奴だっていんだから。そんな化け物に会ったのに、助かってるんだ、俺たちは」
「でもさー高嶺ー」
和端が寒そうに腕をさすった。
「俺、平和主義者だからさぁ」
「そんなの、俺だって同じだろ」
ため息まじりに言って、高嶺は弥帋へと視線を移す。
「これから、どうしたらいい?」
「殀愧と遭遇するのは偶然の確率に過ぎない。僕が出会ったのも、高嶺くんが出会ったのも、和端くんの元に来たのも、すべて偶然だ。殀愧はその時その場にいる獲物を狙う。そこに計算は存在しない。これまでの事件をデータとして分析してみると、そういうことになる。ただ、魅魔の存在は無視できない。魏魔や眩魔とは違い、魅魔には高度な知能がある。和端くんをターゲットとするなら、これからも狙ってくる可能性は高い。発見が偶然起こったことだしても、これからの遭遇は決して偶然とは片付けられないだろう」
「じゃあ、俺は狙われなくても和端は狙われるってことかよ」
「そういうことになるだろうね」
「冗談じゃないよっ!」
和端が突然声を荒げた。本気で目がおびえていた。狙われているという事実に耐えかねているようだった。昼間のことを思い出してしまったのかもしれない。
「和端」
高嶺が戸惑って呼ぶ。
「狙われてるって言われて、ハイそーですか、なんて言えると思う? そんなの納得できると思う? それで策がなんにもなくて、黙って殺されるの待ってろってこと? やだよ、そんなの。嫌に決まってんじゃんっ。なんで俺だけ狙われんだよっ」
「和端、落ち着け」
「やだよっ。なんで落ち着いてられんだよっ。明日殺されるかもしんないし、今夜殺されるかもしれないんだよっ? 高嶺の作るおいしいごはんも食べられなくなっちゃうんだよ? 可愛い女の子とつきあうことだって、できなくなっちゃうんだよ? そんなの冗談じゃないだろっ。許せないだろっ」
「和端、それちょっと論点がズレてる」
「うるさいっ」
いつの間にか和端は立ち上がり、ゼーハーと肩で息をしていた。完全に興奮状態となっており、神経がたかぶっていた。それから突然泣きだしそうな表情に顔を歪めて、ダーッと走り出して部屋に飛び込んで行き、中にこもってしまった。
「……」
高嶺は何と言ったらよいのか、しばし迷った。
感情が乱れる気持ちはわかるが、リアクションが何か違うような気がする。
閉ざされた部屋の扉を表情も変えずに見ていた弥帋が、口を開いた。
「とにかく和端くんがターゲットとして殀愧に決められた可能性は強い。僕の力で役立つことがあれば、出来る限り協力するよ」
「その力でさ、殀愧ってヤツ、ぶっつぶせねぇの? 片っ端から」
「それはさすがに無理だよ。僕の力にも限界というものがある」
弥帋はゆっくりと立ち上がり、和端の部屋のドアへ向かって歩いた。
一度、振り向く。
「とりあえず今夜は、和端くんの部屋に泊まらせてもらうよ。用心棒代わりにね」
和端の部屋をノックすると、ドアはあっさりと開いた。弥帋ならば心強いと思ったのか、和端はすんなりと中に入れる。どうも部屋の中で泣きじゃくっていた様子がチラリと見えて、高嶺はわずかに眉をしかめた。弥帋が中へ入ってドアが閉まると、家ごと静まり返る。
しばらく居間に立ち尽くしていた高嶺は、不満そうに呟いた。
「俺には用心棒いねーってわけ?」
いいけどさ別に、とぼやいて、高嶺も自室に入って行った。