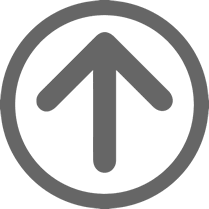(執筆日:1998年02月08日)
駅のホームのベンチにふたり並んで座っていた時、ふいに和端が口を開いた。
「そういえばさ、今日おかしなことあったんだよね」
「ん?」
結局連れ出されて諦めた高嶺は、秋の心地いい空気に眠くなったような声で返事をした。
「人とぶつかりそうになってさ、それがすごい美形だったんだけど、なんか変な感じがして振り向いた時にはいなかったんだよ」
「曲がり角でも曲がったんじゃねえの」
「そんなのなかったよ」
「じゃあおまえが歩きながら寝てた」
「真面目に聞けよな。本当にいなくなったんだよ忽然と。鳥肌立ったもん」
「ふ~ん……」
どうでもいいことのように、高嶺の返事には力がなかった。怪訝に思って和端が顔を覗き込む。
「高嶺、元気ないね」
「これからのこと考えるだけで暗くなるに決まってんだろ」
「なんでそんなに嫌うかなぁ。女の子と喋ってるの、楽しいよ?」
「それはおまえの話。俺は違う。俺にとって女はうるさい生き物なんだよ」
「高嶺の場合、単なる人間嫌いだろ?」
じろり、と高嶺に睨まれたが、和端は知らん顔をした。
ホームに電車が入ってきた。ふたりは立ち上がり、電車に乗り込んだ。
照明は薄暗いが明るい雰囲気の店で、合コンのメンバーたちはすでに集まっていた。女の子は聞いた通りの五人で、男の数もうまく調整したようで五人だった。高嶺と和端が姿を見せると、女の子たちがざわめいた。明らかに高嶺を見ての反応だった。すでに集まっていた三人の男たちが、少し不服そうな顔になる。
「あちゃー俺たちラスト? みんな早いねー」
放すと逃げそうなので、和端はしっかりと高嶺の腕をつかんでいた。嫌々ながらも高嶺は席に座る。女の子たちがはしゃぎ気味になる。
「ねえねえ、誰? こっちのふたり」
おや、と和端が眉をあげた。まさか高嶺とセットで喜んでもらえるとは思わなかったからだ。
田嶋が和端を紹介した。
「で、そっちのがおまえの言ってた奴?」
「そうそう。氷室高嶺くんって言うんだ。カッコイイでしょ? こいつね、いっつも女の子泣かせてて、すごい困ったさんなんだよねー」
「泣かせてねえよ。余計なこと言うなよ」
苦虫を噛みつぶしたような顔で高嶺が文句を言った。
「またまたー。高嶺はこういう場になると、めちゃめちゃ仏頂面になんだから。ほら、笑顔笑顔」
「できるかよ」
そのふてた態度に、女の子たちが何故だか喜んだ。
「和端クンと高嶺クンて、仲いいの?」
雪乃と自己紹介した女子大の子が興味津々に訊く。和端は一瞬きょとんとして、いきなりガバッと高嶺の肩を抱いて引き寄せた。
「こいつと? ええもう、大の仲良し。愛しあってるもんねー俺たち」
語尾にハートマークのつく勢いで言う和端の言葉に、高嶺はくらっと頭痛を覚えた。思わず力任せに突き飛ばす。
「気色わるいこと言うなっ」
「あっはっはー、ごめんごめん」
和端が笑いながら起きあがったところで、
フッと店内の照明が消えた。
一斉にざわめく客たち。和端からも笑みが消えた。
「停電か?」
高嶺がつぶやく。
ザワッと何かを感じた。和端は暗い店内の中で反射的に高嶺を見ると、同じように高嶺が振り向いた。
「なんか変だよね」
「確かにおかしいな」
何がどう変なのかまではわからなかったが、自分たちの感覚が、異様な気配を感じとっている。ずっと前に、同じことがあったような気がした。
しかし真っ暗になった店内で、互いの顔を確認することはできない。それなのに高嶺は和端の位置がわかったし、和端も高嶺の位置がわかった。それが何故なのか考える余裕はふたりにはない。
突然、耳をつんざく悲鳴があがった。ぎょっとした和端は、思わず高嶺の腕をつかむ。強盗か何かかと思ったが、直感で違うとすぐにわかる。だからと言って答えが見つかるわけでもない。
消えた時と同じように、突然明かりがついた。客たちは立っている者もいれば座り込んだままの者もいた。いずれも不安を顔に張り付けて、いったい何が起こったのか周囲を見渡している。どこにも変化はなかった。誰も倒れていないし、怪我もしていない。店の従業員が慌てて客たちをなだめる言葉を吐き出している。原因はたぶん、わからなかったに違いない。口から出た言葉はどう聞いても言い訳だった。
「和端」
ふいに高嶺が呼んだので、和端が顔を向けた。高嶺は茫然とした表情で、向かい側の席を見つめている。つられてそっちを向いた和端は、そこに先ほどまでとは違う光景を見た。
人が足りない。
さっきまで高嶺と和端に興味を向けてきた、雪乃という少女がいない。
椅子の上には、彼女の持っていたバッグが残されており、何故かテーブルの上には片方だけのハイヒールが乗っている。それがいったい何を意味するのか、この場にいる誰にもわからなかった。
「……高嶺、これってさ……まさか」
「かもしれないぜ」
最近、忽然と人が消える。ニュースでも新聞でも頻繁に取り上げられていた。
目の前でまさか、こんなことが起こるなんて。
「彼女……やっぱあのまま行方不明だって」
数日後、大学から帰ってきた和端がぽつんと言った。夜の七時に晩ご飯を食べている最中だった。
「当日、家にも帰ってないって。彼女、実家から通ってた人だから、とりあえず親はしばらく根気強く待ってみたらしいんだけど、駄目なんだって。帰ってこないんだって。警察にも連絡したんだけど、まだ見つかんないんだって」
「……」
高嶺は無言だった。
片方だけ残された白いハイヒール。金品もカードも入ったまま置き忘れられたブランド物のショルダーバッグ。
「昔さ、あったよね、こういう事件。俺たちがまだ高校生の頃。何人も人が消えて、未解決のまま卒業になって、みんなして忘れちゃったやつがさ」
「覚えてたんだ」
高嶺が意外そうに言った。和端が不服そうな顔をする。
「いくら俺でも覚えてるよ? それくらい」
「じゃなくて。あれは、俺がひとりで勝手に見た夢かなんかだと思ってたから」
「なんで?」
和端が問いかける。
高嶺は何かを思いだそうとするような遠くを見る眼差しで、ぽつぽつと喋った。
「いや……なんか、霞がかってんだよな。いろんなことが。そんな事件もあったけど、それだけじゃなくて、他にも何かあった気がすんだよ。でも思い出せねえってことは、何もなかったのかもしれないし……」
「それ、俺も同じだよ。何かあったはずのに、忘れちゃってるんだ。たぶん、思い出せないだけだよ。そういうのって、関係ない時に突然思い出したりするだろ?」
「そうかな……」
ありえない気がした。忘れているというよりも、忘れさせられているような気がしたからだ。
誰に?
「やっぱ……なんか忘れてるよなぁ……」
眉間にシワを寄せて高嶺は考えてみるが、開かない記憶の引き出しが幾つもあるような気がしただけだった。