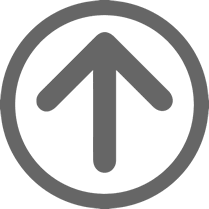(執筆日:1998年08月11日)
手足がバラバラに千切れるような感覚が全身に襲いかかってくる。
落下のスピードに脳がついて行けず、何度か意識が飛んだ。
もう駄目だと頭のどこかが思った。
地面に接触する──。
ガバッとベッドの上に半身を起こし、和端は荒い呼吸を繰り返した。
「……ゆめ?」
現在の自分がどういった状況にいるのか把握できず、和端は乱れた息のまま部屋の中を見渡す。
見覚えのない部屋だった。
「どこだ……ここ」
全身が汗でびっしょり濡れていた。
混乱する頭を軽く振って、和端は思考を巡らせる。
確かベランダから落ちたはずだ。なのに、痛みもなければ怪我もない。
「……たかね」
高嶺はどうしただろう。置いてきてしまった。それよりあれは現実だったのか。
「高嶺に会わなきゃ……」
魅魔が現れて高嶺が操られた。もしもそれが夢なら、今すぐ高嶺に会う必要がある。
現実だとしても、会わなくてはいけない。
「確かめなきゃ……」
妙なことに手足がガタガタと震えてうまく動かなかった。心臓は早鐘を打ち、動揺は消えない。落下の夢を見たせいなのか。
ベッドから降りた和端は、ここがどこだかわからないまま部屋から出ようとした。どことなく豪華というか、格調高い部屋である。装飾品のせいだろう。
ドアを開けると、声をかけられた。
「目が覚めたのかい」
全身で跳ねるように驚いた和端は、声の主を見て、ほうっと息をつく。
「弥帋さん……」
ソファにゆったりと腰掛けて、読書でもしていたらしい。そんな彼の余裕すぎる姿に、和端はかすかな苛立ちを覚えた。
「弥帋さん、あのですねっ。例の殀愧と戦える力とかいうやつですけど、使い方なんて思い出せないじゃないですかっ。全然わかりませんよっ」
激しい勢いで詰め寄る和端を、弥帋は余裕ある態度で見やる。
「自然に身体が使ってくれると言ったはずだが」
「殀愧と高嶺に追い詰められて、落ちちゃいましたよ、ベランダからっ」
そこまで怒鳴って、和端はハッとした。
「俺、なんでここにいるんです?」
「僕に訊かれてもね。気がついたら和端くんが半分意識を失くした状態で、玄関先に立っていたんだ。そのまま倒れ込んでしまったから、部屋に運んで寝かせたんだよ」
「玄関先に立ってた? だって俺、落ちたんですよ、ベランダからっ」
弥帋に訊いても答えは得られそうにない、と思った和端は、そのまま玄関へと向かった。
「どこへ行くんだい?」
「高嶺んとこですよっ。助けなきゃっ」
「よした方がいい」
耳を疑うような言葉が弥帋の口から聞こえて、和端は反射的に振り向いた。
「きみには彼を取り戻すことはできない。なに、力は身についたんだ。自力で切り抜けられるようでないと困るな。きみたちにはこれから、大量にいる殀愧たちと戦ってもらうわけだから」
「……弥帋、さん?」
信じられない、と眼差しで和端は弥帋に訴える。
「俺たちを、はめたんですか?」
「はめたわけじゃないよ。きみたちには元々、殀愧と戦える力が眠っていた。僕よりもよほど強靭な力を持っている。今の世の中には殀愧が溢れ返り、きみたちのような能力を持っている者は他にいない。必然的に、きみたちに動いてもらわないと困るんだ。高嶺くんの内部に魏魔がいることは知っていた。彼がその状況をどう打破するのか、僕はそれが見たくて放置したんだよ。それから忠告しておくけど、殀愧……特に魅魔は、日常生活にまぎれていることもある。周囲の人間に気をつけることだ」
「……」
和端は無言で弥帋を見、踵を返して玄関から出て行った。
ベランダから落ちたにしては、怪我がなかった。
和端はそれが不思議でならなかったが、これが弥帋の言っていた使えるようになった能力なのかもしれない、とムリヤリ納得した。
あの瞬間に、いったい何が起こったのか、覚えていないのでわからない。
和端はズボンのポケットの中を探り、小銭すら持ち合わせていないことに舌打ちした。これではタクシーも使えない。
仕方なく駆け出したが、今が何時なのか知りたかった。
弥帋の部屋で、時計は見てこなかった。それどころではなかった。
ただ、ベランダから落ちた時には夜だったのに、今は朝のようだ。弥帋の部屋でずっと眠ってしまっていたのだろうか。
「あれ? 宮野じゃん」
走りはじめてしばらくした頃、突然、聞き覚えのある声で呼び止められて、和端は足を止めた。
振り返ると、道沿いに建っているコンビニエンスストアから、田嶋久志(たじまひさし)が出てきたところだった。
「……なにやってんの、こんな朝っぱらから?」
意外な時間に意外な人物と出会ったので、和端はわずかに眉を寄せる。
なんとなく、会いたくなかったな、と思う。
この不快感はいったい何だろう。
何故、彼のことが苦手だと感じるのだろう。
考えたところで答えは見つからず、和端は表情を改めて向き直った。
田嶋はそんな和端の様子には気づかなかったようで、やれやれと言った顔で頭をかいた。
「それがさぁ。夜中か明け方みたいな時間に、妙に早く目が覚めちまって、暇でしょうがないからコンビニで本立ち読みしてたんだよ。そんな時間にやってんのって、コンビニかファミレスくらいだろ? 嫌んなっちゃうよなぁー」
「ふうん。そりゃ大変だねー」
適当な相槌をして、和端は挨拶もそこそこに場を離れた。田嶋に付き合ってる暇はない。今ごろ高嶺はどうしているのか、それしか頭になかった。
田嶋と別れてマンションまでの道を走り続け、あと三分くらいで着くかと思われたころ、和端は唐突に足を止めた。
全身を何かにつかまれるような感覚が襲った。
「あ、れ?」
おかしな事実に直面する。
後ろを振り返るが、何もない。
当然だった。田嶋と別れてから、十分くらいは走っている。
「なんであいつが、いるんだ?」
田嶋の家は、電車で一時間先のところにあるのに。
和端は立ち止まったまま考えていた。
気にするほどのことではないのかもしれない。
単に、友人か彼女の家に泊まっただけかもしれないのだ。
気を取り直して、和端はマンションに向かう。
エレベーターに乗り込み、六階まであがった。
何も考えずにまっすぐ部屋を目指した。ドアの前まで来ると、呼び鈴を押す。
待っても反応がないから、さらに押した。
五回押しても、反応がなかった。
「高嶺っ。いるなら出て来いっ」
やや乱暴にドアを叩くが、中からは何のいらえもない。
ドアノブをつかんだ。まわしてみるが、鍵のかけられてある手応えがあるばかりだ。
何の準備もなく部屋から追い出された和端なので、当然、合鍵は持っていない。
踵を返して、エレベーターで一階の管理人室へと向かった。
管理人室から合鍵を借りて、和端は六階に戻った。今度こそ、鍵をはずしてドアを開ける。
玄関に足を踏み入れた。部屋の奥からは何の音も聞こえず、誰かいるような気配もなかった。
「高嶺?」
居間を挟んで高嶺の部屋と和端の部屋がある。和端はまず、高嶺の部屋のドアを開けてみた。
誰もいない。
几帳面な高嶺のベッドは綺麗なままで、ここで睡眠を取った気配はない。
和端は自分の部屋のドアを開けた。
やはり誰もいない。
「どこ行っちゃったんだよ、高嶺……」
がっくりと肩を落として、和端は自分のベッドの端に座り込んだ。
「嫌われたかな」
雑誌を繰りながら、弥帋はぽつりと呟いた。
だが、和端に語った言葉に偽りはない。似たような力を持ってはいるが、弥帋よりも彼らふたりの方がより強い能力を持っている。
このまま殀愧を放置しておけば、わずかしかいないラーヴァの生き残りがすべて食料にされてしまう危険がある。それも事実だ。
そのような事態を回避するためには、反撃しかない。
殀愧がどれほどこの世界に紛れ込んでいるのか定かではなかったが、指をくわえて食料にされるのを待つ気はさらさらなかった。
通常の人間と違って、ラーヴァの人間の魂には力がある。本来なら存在しなかったはずの魅魔も、ラーヴァを喰らった魏魔から進化した姿だ。
殀愧というのがどのような存在なのかは、弥帋も詳しく知らない。ただ、自分たちを脅かす敵であることに間違いはなかった。
ラーヴァの生き残りで見つけたのは、まだふたりのみ。
同様に、殀愧たちもまだあのふたりしか見つけていないようだった。
弥帋は膝の上の雑誌を閉じた。ソファに腰を沈めたまま、カーテンの閉まった窓を眺めやる。
「おや」
弥帋がわずかに驚嘆した声で呟いた瞬間。
派手な音を立ててガラスが割れた。
風が吹く。カーテンが舞いあがり、割れたガラス戸が見え隠れする。
ガシャ、と割れたガラスの上を踏みしだく音が聞こえたかと思うと、ゆらりと人影が現われた。
「これはこれは……いらっしゃい」
弥帋はわずかな警戒をしつつも、普段の落ち着いた態度を失わなかった。
尋常ではない目つきで弥帋へと視線を向けたのは、他ならぬ氷室高嶺である。
「……シグマ」
呂律のまわらぬ声で、高嶺は静かに言った。
弥帋は落ち着き払った態度を変えぬまま、高嶺と相対する。
戦う気はない。しかし高嶺の方がそうであるか否かはわからない。
「シグマ、だな。おまえ……」
「その通り。そしてきみはラムダだ。きみと一緒に暮らしている和端くんはデルタ。偶然ながら、三人ものラーヴァが遭遇してしまった。まさかきみはこうなるとは考えてもみなかったんだろうがね」
高嶺はフラリとおぼつかぬ足取りで、一歩踏み出した。
「偶然?」
怪訝そうな声で、高嶺が呟く。そこには怒りが含まれている。
「本気で偶然だと思っているのか」
たぎるような怒り。背中で炎が燃えあがるのではないかと思われるほどの。
弥帋はさらに一歩引いた。
「きみは殀愧に操られているのではなかったのかい? ずいぶんとまともな言葉を吐く。すべてを思い出したからと言って、僕に当たるのはやめてほしいな。もとはと言えば、本来悪いのはラーヴァに侵略してきた殀愧どもだ。もしもあのような状況にならなければ、僕もあのような真似はしなかった」
「ぬけぬけと……」
高嶺の怒りは深いが、身体が思うように動かなかった。彼の内部では魏魔とのせめぎ合いが続いている。これでもかなり自分を取り戻しているつもりだった。
「なるほど、ラムダは心底からおまえが憎いと見える。よほどあの時、殀愧に喰われてしまった方が幸福だったのではないか?」
高嶺の背後から現われたのは、人間離れした美しさを持ちながらも、まがまがしい空気をまとった魅魔であった。薄く笑いながら、高嶺の傍に足を止める。
弥帋は小さく笑った。
「ずいぶんと中途半端だな、高嶺くん。僕とまともな会話しながらも、その実、殀愧に操られたままなのか。きみが本来怒りを向けなくてはならないのは、殀愧の方だよ。僕は何ひとつ悪いことはしていない。きみを傷つけたかもしれなくてもね」
ゆらり、と高嶺が動く。ガクリと膝を落とした。力が入らなくなったようだ。
「和端には……近づくな」
眼差しだけが鋭く弥帋を睨みつける。
激痛が全身に走った。
「うあ……っ!」
「無理をするから、そんな風になる。内部にある魏魔を排除してから僕に文句を言うといい。その時には存分に相手をしてやるよ。……さて」
弥帋は視線を魅魔の方へ移した。
「そちらはどのような用でここに来たのかな」
「ラムダの後を追ったにすぎない。まさかおまえのところに着けるとは思いもしなかった。往生際の悪いラーヴァの生き残り。他にもまだいるのだろう? おまえなら知っているはずだ」
魅魔は不穏な笑みを消さぬまま言葉を紡ぐ。
対して、弥帋は笑み返した。
「過信されても困るな。いくら僕でもそこまでは知らない。それにおまえたちも、他のラーヴァは喰えても僕だけは喰らえない。理解しているはずだと思うが」
「だから余計な攻撃はせずにこうして話などをしておるのだ」
高嶺は、唐突に傍に立つ魅魔が誰なのか悟った。苦痛に顔を歪めさせながら、ゆっくりと見上げる。
「……ファイ」
一瞬にして過去の姿が見えた。殀愧に取り込まれる以前の、魅魔の本当の正体。
幼いラムダに優しくて、隣に住んでいた……。
そこまで思い出して、高嶺の意識が白濁した。魏魔の意識が邪魔をする。また乗っ取られるのかと無意識に感じる。
(俺は殀愧の配下じゃない!)
もう操られるのはたくさんだ。その願いも空しく、高嶺の意識は底へ沈んだ。